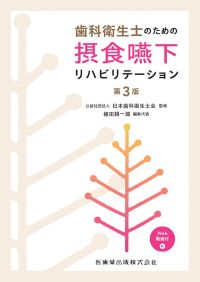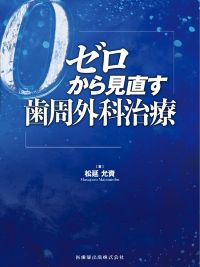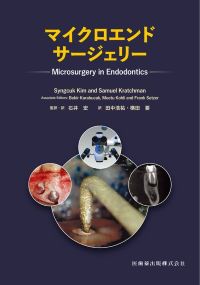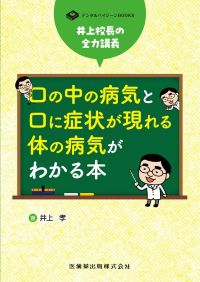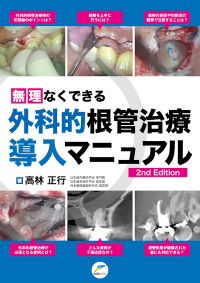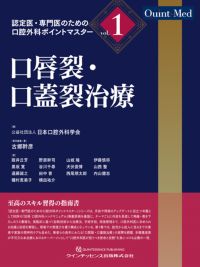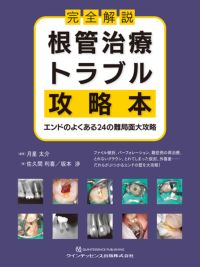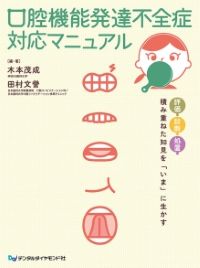| 書籍案内(出版社順) |
書籍画像 |
歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリテーション
第3版 Web動画付
定価4,620円(本体4,200円+税)
B5判・328頁・二色刷
摂食嚥下リハビリテーションを歯科衛生士の視点から整理・解説し,体系的にまとめた好評書の全面改訂版.
動画付きになりさらに分かりやすく!
【内容紹介】
●摂食嚥下リハビリテーションの領域において,口腔に関するスペシャリストである歯科衛生士がいつでも現場で対応できるよう,摂食嚥下機能の基礎的な知識から摂食嚥下リハビリテーションの実践的な手技までを体系立て解説しています.
●今改訂では,制度改正,最新のエビデンス,現場からの要望に応えるかたちで内容をさらに深化・再構成しました.
●さらに,摂食嚥下の実際や評価,訓練法についての動画が加わり,理解が深まります.
【目次】
Ⅰ 基礎編
CHAPTER 1 歯科衛生士と摂食嚥下リハビリテーション
CHAPTER 2 リハビリテーションと摂食嚥下リハビリテーション
CHAPTER 3 高齢社会の制度の理解と口腔健康管理
CHAPTER 4 摂食嚥下機能のメカニズム
CHAPTER 5 咬合および咀嚼機能の管理と評価
CHAPTER 6 栄養管理
CHAPTER 7 病態別摂食嚥下障害
Ⅱ 臨床編
CHAPTER 1 リスクマネジメント
CHAPTER 2 摂食嚥下リハビリテーションの実際
CHAPTER 3 口腔衛生管理
CHAPTER 4 薬剤と嚥下障害
CHAPTER 5 摂食嚥下障害者への症例展開
2025年9月20日発行
医歯薬出版
|
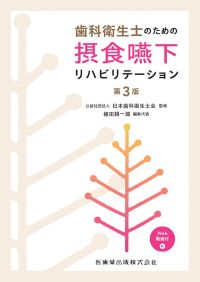 |
ゼロから見直す歯周外科治療
定価9,900円(本体9,000円+税)
A4判変型・124頁・カラー
なぜ,歯周外科が上手くいかないのか?
誰にでも治療を進められる極意がここに
【目次】
第1章 歯周外科治療の適応症を見直す
はじめに
歯周基本治療の標準的な進め方
歯周外科治療の適応
歯周基本治療の重要性
歯周外科治療のラーニングステージ
第2章 歯周外科治療の基本手技を見直す
はじめに
歯周外科治療を行ううえでの基本知識
浸潤麻酔
ボーンサウンディング
替え刃メスによる切開
ペリオナイフによる切開
歯肉弁剥離
デブライドメント
縫合
歯周パック
術後管理
第3章 歯周外科治療の術式を見直す
はじめに
従来の歯周外科治療の分類と歯周外科後の治癒
組織付着療法の術式について考える
筆者の考える歯周外科の分類と術式
2025年9月20日発行
医歯薬出版
|
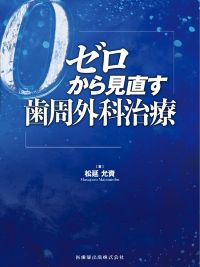 |
マイクロエンドサージェリー
定価33,000円(本体30,000円+税)
A4判・200頁・カラー
世界の臨床歯内療法をリードするペンシルベニア大学の執筆陣による,外科的歯内療法の成書の日本語版
【内容紹介】
・マイクロエンドサージェリーの専門家による最新かつ実践的な解説
・理解が深まる豊富な臨床写真とイラスト,信頼できる参考文献を掲載
・使用器具,症例選択,治療のテクニック,トラブルの予防と対応,治療成功の評価など,マイクロエンドサージェリーに関するあらゆるトピックをカバー.この1冊でマイクロエンドサージェリーのすべてがわかる!
【目次】
1 歯科用マイクロスコープ
2 マイクロサージェリー用インスツルメント
3 薬剤関連顎骨壊死とマイクロエンドサージェリー
4 適応と禁忌
5 麻酔と止血
6 マイクロエンドサージェリーにおけるフラップデザイン
7 骨窩洞形成
8 歯根端切除
9 歯根切断面の検査─イスムスへの対応の重要性
10 超音波チップによる逆根管形成
11 逆根管充填材─MTAとバイオセラミック系材料
12 フラップの復位と縫合
13 根尖周囲の創傷治癒
14 コーンビームCT
15 オトガイ神経の管理
16 上顎臼歯部の歯根端切除術─上顎洞穿孔への対応とパラタルアプローチ
17 外科的パーフォレーションリペア
18 意図的再植術
19 マイクロエンドサージェリーにおけるGTR法
20 インプラントvsマイクロエンドサージェリー
21 マイクロエンドサージェリーの予後
22 ポジショニング
2025年9月20日発行
医歯薬出版
|
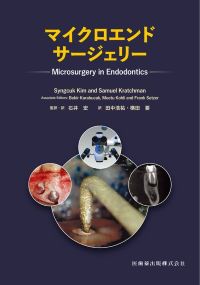 |
エンド・ペリオ・外科に役立つ
日本人の歯根・根管形態ビジュアルブック
定価8,800円(本体8,000円+税)
A4判変型・152頁・二色刷
日本人の歯根と根管,上下顎骨,上顎洞,下顎管,形態異常歯のデータを“やさしく”ビジュアルにまとめた決定版!
【内容紹介】
●形態学の臨床研究を長年ライフワークとしてきた著者がまとめた“令和のビジュアルブック”です
●あらゆる歯科臨床の基礎を支え,歯科医師・歯科衛生士の診断,治療技術向上のための一助となる一冊です
【目次】
まず押さえておきたい基本情報
歯に関する基本情報
歯根・根管形態の画像診断法について
本書で用いた分類
日本人の歯根・根管形態 Ⅰ 上顎
上顎前歯
上顎小臼歯
上顎第一大臼歯
上顎第二大臼歯
上顎第三大臼歯
日本人の歯根・根管形態 Ⅱ 下顎
下顎前歯
下顎小臼歯
下顎第一大臼歯
下顎第二大臼歯
下顎第三大臼歯
あわせて知りたい関連知識
形態異常歯
歯槽骨のフェネストレーション
歯科用コーンビームCTで観察される上下顎骨の解剖構造
2025年9月15日発行
医歯薬出版
|
 |
臼歯部コンポジットレジン修復
─MI時代の臨床戦略─
定価11,000円(本体10,000円+税)
A4判・148頁・カラー
ここまできた!
臼歯部コンポジットレジン修復の臨床戦略
【内容紹介】
・コンポジットレジン材料の進化により,臼歯部の直接修復においても,高い予知性と長期安定性が得られる時代が到来しています.
・本書では,臼歯部におけるMI修復のための器具機材と技術を実践的に紹介.各執筆者が考案したテクニックも供覧し,次世代の修復治療を目の当たりにできます.
・若手はもちろん,日々の臨床でさらなる技術向上を目指す歯科医師にも確かなヒントを提供する一冊です.
【目次】
Chapter 1 どこまでいける? コンポジットレジン
Chapter 2 形態をつかむ!
Chapter 3 接着修復の基本-防湿・接着-
Chapter 4 治療介入する・しない?
Chapter 5 コンポジットレジン修復のテクニック-マトリックスフリーorマトリックスワーク-
Chapter 6 臨床例
2025年9月10日発行
医歯薬出版
|
 |
デンタルハイジーンBOOKS
井上校長の全力講義
口の中の病気と口に症状が現れる体の病気がわかる本
定価4,950円(本体4,500円+税)
B5判・104頁・カラー
井上校長のおもしろくてためになる「病気の授業」開講!
【内容紹介】
・月刊『デンタルハイジーン』の2つの好評連載を,前後期の講義として1冊にまとめました!講師は病理学の達人,井上孝先生!
・前期の授業は,歯周病を中心に,口の中の病気を一般社会に例え,イラストを使ってわかりやすく解説!
・後期の授業は,口腔にトラブルが現れる体の病気をストーリーで解説していきます!
・本講義で,口の中の病気の成り立ちと,口に関わる体の病気を知れば,臨床の役に立つこと間違いなし!
【目次】
【前期】 口の中の病気の授業
第1講 身体の中を「社会」に例えると?
第2講 「上皮」は一筆書きでできている!?
第3講 「傷」ができたら生体はどうやって治す?
第4講 齲蝕は生体が治せない歯の「傷」
第5講 歯周病は歯と歯肉の間の「傷」
第6講 歯周病の原因になるPg菌ってどんなヤツ?
第7講 歯周病にまつわる免疫のしくみ
第8講 歯周病の症状が出るワケ
第9講 歯周病の検査と医療面接
第10講 歯周病の治癒を阻害するのは細菌と異物
第11講 歯周治療後の治癒形態とGTR法
第12講 歯周病のメインテナンスが欠かせないワケ
第13講 歯周組織再生療法とは
第14講 幹細胞による歯周組織再生療法の未来
第15講 インプラント周囲炎は歯周病とどう違う?
【後期】 口に症状が現れる体の病気の授業
第1講 口臭が消えません!
第2講 味覚異常が治りません!
第3講 口内炎が治りません!
第4講 白色病変が治りません!
第5講 カリフラワー状の病変が治りません!
第6講 子供の口に白斑が!
第7講 抗凝固薬を服用しているのに血が止まるのは……?
第8講 腫瘤が硬いです
第9講 首のしこり,原因は……?
第10講 タオルが原因で……?
第11講 こんな患者さんも気をつけて! 咳が止まりません
第12講 こんな患者さんも気をつけて! 顔が真っ青!
補講1 講義で取り上げた口に症状が現れる疾患のまとめ
補講2 口に症状が現れるその他の重要な疾患
2025年9月10日発行
医歯薬出版
|
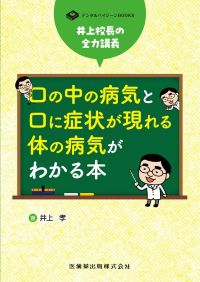 |
これからはじめる
歯科訪問診療の摂食嚥下リハビリテーション
定価6,930円(本体6,300円+税)
A4判変型・108頁・二色刷
歯科訪問診療で摂食嚥下リハビリテーションに取り組むために,まず読んでおきたい一冊
【内容紹介】
・歯科訪問診療の対象となる患者は,同時に摂食嚥下機能にも問題がある場合が多く,歯科医師は観察力と技術をもって対応することが求められます.
・本書は歯科が訪問診療の際に,患者が置かれた状況を理解し,摂食嚥下障害に対して取り組みを進められるよう,執筆陣の実践をイラストを交えて紹介した書籍です.
・摂食嚥下障害への対応には,多職種との連携が欠かせません.本書では嚥下食に造詣の深いシェフのレシピも掲載.歯科訪問診療に華を添える一助となります.
【目次】
第1章 はじめに―モヤモヤを解消していこう!―
第2章 歯科訪問診療における摂食嚥下リハビリテーション
第3章 摂食嚥下障害とは
第4章 歯科訪問診療における摂食嚥下障害の評価
第5章 歯科訪問診療における摂食嚥下リハビリテーション―調整,訓練,歯科治療
第6章 症例から学ぶ歯科訪問診療の特徴
第7章 これからの摂食嚥下リハビリテーションを考えてみる
特別付録1 歯科訪問診療の摂食嚥下リハビリテーション そのバッグの中身は!
特別付録2 野田シェフ直伝 美味しく楽しむ摂食嚥下食レシピ
2025年8月25日発行
医歯薬出版
|
 |
無理なくできる外科的根管治療導入マニュアル
2nd Edition
定価9,020円(本体8,200円+税)
A4判・116頁
「外科的根幹治療のバイブル」として大好評の本書が 2nd Edition にバージョンアップしました!
▶掲載症例の見直し&難症例の対応例を追加
▶最新かつ入手可能な器具・機材に更新
これまで以上に外科的根幹治療の臨床導入をサポートします!
外科的根幹治療の臨床導入にあたっての疑問点をスッキリ解決!
・外科的根幹治療が必須となる症例とは?
・どんな症例が不適応症なの?
・根幹形態が破壊された歯にも対応できる?
・外科的根幹治療時の切開線のポイントは?
・剥離を上手に行うには?
・歯根表面や切断面の観察で注意することは?
【Contents】
Chapter1 外科的根管治療に対するイメージを変えよう!
Chapter2 外科的根管治療の適応症
Chapter3 ビギナーは要注意 外科的根管治療の難症例
Chapter4 外科的根管治療の基本術式
Chapter5 臨床導入のイメージ
Chapter6 治療の実際を臨床例からイメージしよう
2025年8月29日発行
インターアクション
|
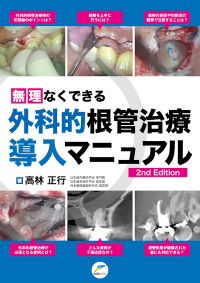 |
Quint-Med
認定医・専門医のための口腔外科ポイントマスターvol.1
口唇裂・口蓋裂治療
定価14,300円(本体13,000円+税)
A4判変型・164頁
口腔外科臨床および学会資格取得にも役立つ待望のサブテキスト第1弾刊行
関係者の必携書として年1回刊行の『別冊 口腔外科ハンドマニュアル』掲載原稿を基盤に、テーマごとに内容を再編・書き下ろしのうえ書籍化したポイントマスターシリーズの第1巻。
筆者らの長年にわたる口唇裂・口蓋裂治療の実際をもとに、疾患の機序や手術手技、関連する治療法、胎児から成人に至るまでの患者や家族の精神的ケア等も含めて網羅。
多職種連携が不可欠な本治療における口腔外科医に必要な知識と技術の習得に役立つ1冊。
【CONTENTS】
序章 用語の定義と疾患の分類
第1章 疾患の機序と基本事項
1 疾患の成り立ち
2 鼻咽腔閉鎖機能
3 口唇裂・口蓋裂治療における矯正歯科治療
第2章 診療体制および診断
1 チーム医療
2 出生前診断とケア
3 出生時診察とケア
第3章 手術の実際
1 口唇裂・口蓋裂治療の流れとコンセプト
2 術前顎矯正治療
3 口唇裂の手術
4 口蓋裂の手術
5 顎裂部骨移植術
6 口唇外鼻二次修正術
7 咽頭弁移植術
8 顎変形症手術
9 手術における問題点・注意事項への対応
第4章 医学的管理と支援の実際
1 術後管理
2 長期管理の要点
終章 長期治療成績からみえてくるもの
2025年9月10日発行
クインテッセンス出版
|
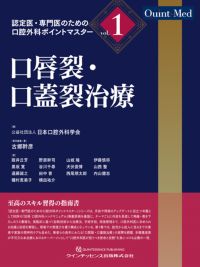 |
咬合の臨床応用
アナログからデジタルまで
定価12,100円(本体11,000円+税)
B5判変型・200頁
深遠な歯科咬合学をシンプルに説き、日常臨床に活かすことができる1冊!
補綴臨床において、患者の現在の咬み合わせでは必要な治療が行えないことがある。
その場合、どうやって新たな咬合関係を構築するのか?
患者がその関係を(たとえば患者が心地よいと感じる咬み合わせで)決めるのか?
それとも、生理的な上下顎間関係を見つけ出すという科学的原則を基に決めるべきか?
新しい咬合関係をどうやって記録し、歯科技工所に伝えるか?
本書は、治療を成功裏に行うための咬合の概念をシンプルに解説している。
【目次】
1部
1章 われわれにはなぜ,咬合が必要なのか?
2章 咬合の実践原則
3章 咬合の公式
4章 咬合は2種類しかない
2部
5章 咬合採得の原則とその手法
6章 検査と治療計画立案法
7章 既存の咬合関係での咬合採得法
8章 新たな咬合関係を付与するための咬合採得法
9章 咬合調整法
10章 機能的運動範囲の採得法
11章 歯科技工所とのコミュニケーション法
12章 咬合採得におけるアナログとデジタルの比較
2025年9月10日発行
クインテッセンス出版
|
 |
完全解説 根管治療トラブル攻略本
エンドのよくある24の難局面大攻略
定価9,900円(本体9,000円+税)
A4判変型・136頁
根管治療の困ったときに、これ1冊! 臨床で使える、実践的なコツが満載!
根管治療は繊細な手技が要求される。見えにくい部分でもあり、治療歴の多い患者は口腔内に複数リスクがあるため、臨床経験を積んでもトラブルとなることは多い。
本書は経験の浅い歯科医師も上達しやすいよう、エンドでよくある24の難局面の臨床例をもとに、イラストや写真を多用し、手技だけでなく治療の進め方など攻略法を解説。
適切な治療に必要な基礎知識、経過観察のポイント、使用ツールや材料の使い方のコツも網羅した。
【CONTENTS】
PART 1 根幹治療時のトラブル
PART 2 再根幹治療時のトラブル
PART 3 その他のトラブル
2025年9月10日発行
クインテッセンス出版
|
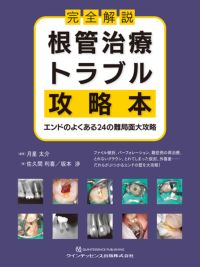 |
“知らなかった”で困らない
デンタルスタッフの新社会人ワークブック
定価4,400円(本体4,000円+税)
B5判・128頁
書き込んで理解する! 社会人1年目のための歯科の社会常識ワークブック
30年にわたり歯科医院のコンサルテーションを行ってきた濵田さんが、新人歯科衛生士から実際に相談されたお困り事例の解決の秘訣をまとめたワークブックです。
お金に関する悩みには2級ファイナンシャルプランニング技能士の山上さんが解説します。
歯科への就職が決まった新人必携の1冊で、院長から新人へプレゼントすれば、院内でのすれ違いも未然に防げるかも。
見開き完結で、隙間時間に読めるのもポイントです。
【もくじ】
はじめに
第1章 たいどのワーク
第2章 ことばのワーク
第3章 スキルアップのワーク
第4章 くらしのワーク
第5章 おかねのワーク
おわりに
column
2025年9月10日発行
クインテッセンス出版
|
 |
口腔機能発達不全症対応マニュアル
評価・診断・処置 積み重ねた知見を「いま」に生かす
定価7,700円(本体7,000円+税)
A4判変型・148頁・カラー
【概要】
保険収載から7年
これまでを振り返り、これからの臨床に生かそう!
「口腔機能発達不全症」は、平成30年(2018年)の公的医療保険の診療報酬改定において保険医療の対象病名として収載されました。
以降、多くの臨床家が「食べる機能」、「話す機能」など機能面について注力してきましたが、口腔機能発達不全症の適切な評価や診断、対応について悩まれるケースもみられます。
本書では、口腔機能発達不全症の成り立ちから保険対応、問題点の解釈や評価、そして多職種連携等、具体的な事例を供覧しながら総合的に解説しています。
口腔機能発達不全症の臨床において、問題点を指摘するだけで終わることのないよう、改善策を提示し、家族と一緒に悩み支えていく医療を行うために、ぜひ本書をご活用ください。
【こんな方におすすめです。】
・口腔機能発達不全症の保険請求を今後進めていきたいとお考えで、基本を知りたいという先生方におすすめ
・積極的に保険点数を請求されている先生方の、実践的知見を参考にしたい先生方におすすめ
・口腔機能発達不全症のこれまでの歩みを振り返り、改めて学び直したい先生方におすすめ
【CONTENTS】
第1章 評価・診断・保険算定の基本
1.口腔機能発達不全症の基本~保険収載から現在までを振り返って
2.チェックリスト(離乳完了前)使用時のポイント
3.チェックリスト(離乳完了後)使用時のポイント
4.算定可能な保険点数と請求時の注意点
5.口唇閉鎖力検査
6.舌圧検査
7.食べる機能の評価
8.口腔機能の発達を促す食事と姿勢の指導
第2章 対応・アプローチの基本
1.一般開業医でできる運動機能訓練
2.MFTで小児の口腔を育てよう
3.食行動への対応
4.構音機能への対応
5.栄養(体格)への対応
6.呼吸への対応
第3章 ケーススタディ ~評価・診断・対応・保険請求まで
1.硬い食べ物を拒否する子に対する食事を支援したケース
2.姿勢を中心に対応したケース
3.食べる機能を支援したケース
4.効果的な小児口腔機能管理のポイント
5.発音の問題への対応に苦慮し言語聴覚士との連携にシフトした一例
6.離乳食を食べない・嫌がるケース
2025年9月1日発行
デンタルダイヤモンド社
|
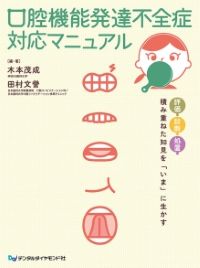 |
歯科のための位相差顕微鏡
活用・実践マニュアル
定価6,930円(本体6,300円+税)
A4判変型・112頁・カラー
【概要】
口腔内の細菌叢をリアルタイムに可視化することで、歯周病のリスク診断補助や治療前後の評価に活かす。
さらには、患者教育やモチベーション維持にも!
“百聞は一見にしかず”です。
歯科においては近年、CBCT、マイクロスコープ、IOSなどの先端技術を導入した治療技術が浸透し、術者も患者もその恩恵に浴しています。
本書では、新たなアイテムとして歯科のための位相差顕微鏡の活用について取り上げました。
位相差顕微鏡は予防歯科を冠している歯科医院にはいまや欠かせないものとなっています。
歯科医院では以下の目的で活用・実践がなされています。
①細菌の種類や活動性をリアルタイムで観察することで歯周病などのリスクを推測して治療方針の決定に寄与する。
②治療前後の細菌叢の変化から改善状況を確認する。
③細菌の状態を患者と共有することで、患者のモチベーション維持に活用する。
本書では、位相差顕微鏡の基本、観察方法のコツ、細菌たちの特徴、臨床への応用方法、そして未来への可能性について最新の情報を交えながら紹介しています。
ぜひ、予防歯科の新たな潮流に注目してみてください。
【おすすめポイント】
・CBCT、マイクロスコープ、IODなどの最新機器に加えて、新たな歯科のアイデムとして位相差顕微鏡を取り入れたい方へ
・予防歯科(検査)に力を入れている歯科医院の歯科医師、歯科衛生士、スタッフの方へおすすめです
【CONTENTS】
刊行にあたって
位相差顕微鏡に関する基礎知識
Chapter 1 位相差顕微鏡を歯科で活用する
Chapter 2 正しい検体採取と標本作成
Chapter 3 口腔細菌の典型的な正常像と異常像
Chapter 4 代表的な細菌とその特徴
Chapter 5 位相差顕微鏡による観察の限界と注意点
Chapter 6 臨床への応用方法
Chapter 7 これからの可能性と未来展望
2025年9月1日発行
デンタルダイヤモンド社
|
 |